愛の奉仕活動紹介
愛の奉仕活動紹介: Vol.21 社会福祉法人ロザリオの聖母会
2024年12月19日
「社会福祉法人ロザリオの聖母会」訪問レポート
今回は、千葉県旭市に本部を置く社会福祉法人ロザリオの聖母会を訪問しました。ロザリオの聖母会は千葉県東部の旭市と香取市で海上寮療養所という精神科の病院をはじめ、重度心身障害・知的障害・身体障害等様々な障害をお持ちの方々に入所・通所等様々な形での支援を提供する24の施設を運営しています。この日は、九十九里海岸に近い旭市野中にある法人本部で石毛敦理事長にお話を伺いました。

社会福祉法人ロザリオの聖母会の法人本部棟です。
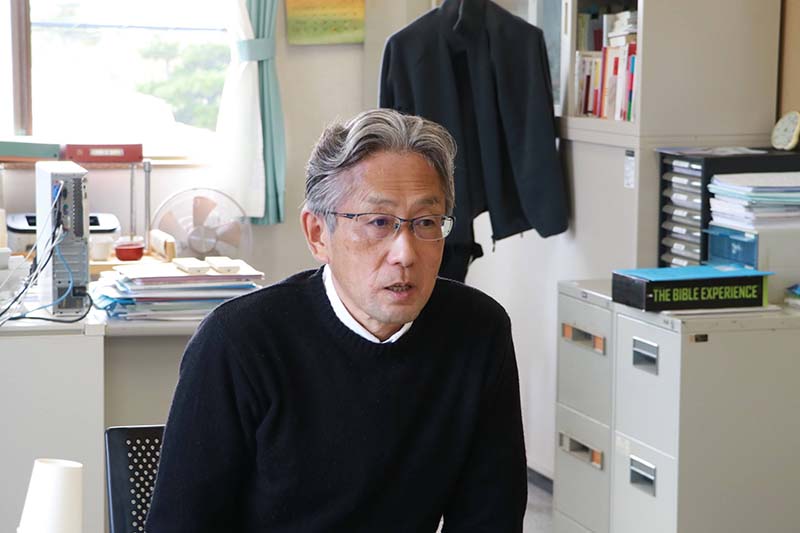
インタビューにお答えいただく石毛理事長です。
ロザリオの聖母会の歴史は戦前の戸塚神父様によるナザレトハウス(結核療養施設)開設までさかのぼるとのことですが。
戸塚文卿神父様は暁星中学を首席で卒業後、第一高等学校、東京帝大医科大学に進学して医師となり卒業時に恩師の銀時計を授かり、東京帝大医科大学助手、北海道帝国大学助教授に就任、文部省から国費で2年間フランス、ドイツ、アメリカへの留学を命じられ、パリのパスツール研究所で組織学を研究、その後ロンドンに滞在していた時に召命を受けてパリのサン・スルピス神学校に入りました。ロンドン時代にシスター・ローズ、バイオレットと懇意になり、ボンサマリタンという布教や慈善を目的とした会を創設しました。1924年に司祭に叙階、1925年にシスター・ローズ、バイオレットを伴い、母国で医師という立場も使いながら宣教活動をしようと決意し帰国したそうです。最初は実家の病院を引き継ぎ「聖ヨハネ汎愛病院」として開院、次いで1929年に品川の荏原に結核療養所ナザレトハウスを開き結核患者を診ていました。同年には武蔵関のカトリック神学院教授に就任し自然科学を教授、1930年には雑誌「カトリック」の編集長に就任しています。それから、結核患者を転地療養するための施設が必要であると考えて、海辺で暖かく気候の良いここ旭市の地を選んで1931年にナザレトハウスを移転しました。このナザレトハウスが病院組織となって海上寮となりました。その後、戸塚神父様は聖母病院の病院長としても活躍され、司祭職も同時に果たしながら1939年には桜町病院を開設しましたが、同年に今までの無理が影響し心臓を悪くし47歳の若さで帰天されました。
海上寮は戸塚神父様の帰天後東京教区が経営を承継しましたが、第二次大戦末期、九十九里海岸に米軍が上陸して戦場になる危険性があるとして廃院されて、施設は日本医療団に売却されました。戦後、1947年にフランシスコ会の司祭で田園調布教会の稲用経雄神父様が教会の4人の女性とともに宗教法人聖フランシスコ友の会を設立して、日本医療団より海上寮を買い戻して結核療養所を再開しました。その後、社会福祉の法制度の改変に伴って、組織は社会福祉法人ロザリオの元后会をへて現在の社会福祉法人ロザリオの聖母会となっていきます。
その後、抗生物質の開発で結核が治療されるようになり療養所の役割が見直されるようになりました。国立系の結核療養所の多くが精神科の病院へと改変されてきた流れに合わせて、海上寮も次第に業態を変えて、1971年に精神神経科の病院となりました。

戸塚神父様が住まわれた建物です。
その後、海上寮の精神科の立ち上げに尽力された医師で東大医学部精神科教授土居先生の居室として使われました。


戸塚神父様の建てられたお御堂です。中は畳敷きの会衆席となっています。


海上寮の外来入口と病棟です。
法人の事業は業態的・地域的にどの様に発展をしてきたのでしょうか。
4人の女性達は海上寮の次の事業として、高齢化に対応した老人ホームの建設を考えたようです。しかし、既にこの地域には老人ホームが数多く存在していたため、行政から地域で必要とされている重症心身障害者の為の施設を建てた方がいいのではないかとアドバイスがありました。そして、それに応える形で重度心身障害施設である聖母療育園を開設しました。それ以降、国の入所系の福祉施設を拡充していくという政策に合わせて身体障害者の入所施設である聖マリア園が開設されました。次に、比較的障害者の方の人数が多い知的障害の施設として聖家族園を開設しました。これが入所系のピークの時でした。
また地域的には海上寮のある旭市から広がり、2001年に香取市には知的障害者の入居施設がないので当法人に建設してもらいたいという市からの要請にもとづいて佐原聖家族園を開設しました。
以上の事業の拡大は行政の流れもありますが、当法人の先々代の細渕理事長が1983年に入職してから不眠不休の活躍で積極的な施策を取ってきたこと、さらには、当時は氷河期世代などマンパワーにも恵まれていた結果でもあります。

重度心身障害施設の聖母療育園の正面玄関です。

障害者支援施設「聖マリア園」です。

障害者支援施設「聖家族園」です。
旭市と香取市で24事業所を運営しているとのことですが、事業の全体像をお話し願えますでしょうか。
事業の説明の仕方として様々な切り口がありますが、利用者の障害種別でいくと精神障害・身体障害・知的障害・発達障害に分けられると思います。
さらには、入所系、グループホーム、通所系という分け方があります。入所系は比較的大きな施設に個室を設けて食住入浴のお手伝いをするものです。私共では海上寮や聖母療育園、聖マリア園、聖家族園、佐原聖家族園がこれに該当します。
グループホームはこの入居系からいきなり社会に出ることが困難な場合に入居する中間施設的なものとなります。グループホームではアパート等を借り上げたり、自前で建設したりした建物の個室で利用者の方に起居する場所と職員が食事の提供等をしています。私共では「ナザレの家あさひ」と「ナザレの家かとり」がグループホームとなっていますが、このあさひには22のグループホームがあり定員は90名となっています。障害が軽度の場合このグループホームから地域社会に出る方もいますが、グループホームに長くとどまるという方もいます。グループホームから出た方は通所系というデイサービスに通ってくる方もいます。国の政策に従って精神疾患の軽度の患者は海上寮からグループホームに移転するようにしました。また、特別養護老人ホームに入るほど障害がない場合も老人用のグループホームに入居します。身体障害の方もお世話する職員は大変ですがグループホームを用意しています。
後、就労系という分野があります。これは、みんなの家やワークセンターのように利用者の方がそこでパンの製造、印刷、調理等で働くことができる施設になります。これらの施設では、外部就労を目的とした職業訓練にとどまらず、この施設自体で働くことの訓練も目的としています。
最後に相談系という様々な地域住民からの相談を受ける施設があります。また、老人と障がい者へのヘルパー派遣も行っています。

本部敷地内の施設配置図となります。

ナザレの家あさひのアパート形式のグループホーム。

ナザレの家あさひの借上マンション形式のグループホーム。

ナザレの家あさひの身体障害用のグループホーム。出入口が広めに設計されています。

高齢者支援センターで作家の有吉佐和子さんのご遺族からの寄付で建てられました。
旭市内の施設の東総地域における位置付けはどうなっていますか。
この地域に当法人ほどの規模の障害者施設はないので、行政からは頼りにされていると思います。隣接する匝瑳市にはイギリス国教会系の九十九里ホームという老人ホームと総合病院を中心とした大きな施設があります。この辺りは地価・人件費・物価が安いことから東京都を初めてして首都圏の自治体の運営する福祉施設があります。
地域社会の中で障害者をケアする流れの中て、居住型施設が担う役割と利用者の状況はどうなっていますか。
行政の方針としてはできるだけ障害者を地域社会の中で看ていくという方針ですが、この主たる目的は福祉予算の削減にあると感じています。軽度の障害の方で地域の中で生活していくのに問題のない人はいますが、一方で障害の為に地域で生活することが難しい人もいます。先程も述べましたが、私共も海上寮から比較的軽度の精神障碍者の方にグループホームへ移っていただきました。精神科の患者さんも最近は薬剤が進歩してきたため社会で暮らせるケースが増えてはいます。しかし、入所して常時看護・介助する必要のある方が一定以上いるのは事実です。この問題を考える時に、地域の中に住むことがその障害者の方にとって幸せなのかという視点で考える必要があり、杓子定規に何が何でも地域でというのは間違っていると思います。さらに、現実的には家族から入居させてほしいという要望が多くあります。親の高齢化等で家族が家庭の中で世話をすることが難しくなっている、あるいは将来的になる恐れがあるということを反映いているのだと思います。この点を考えると、今までは障害者の方を家族が面倒を見ていた場合に施設に入る必要が出てくるようになり、入居系の施設の必要性が増してくることも考えられます。
医療の入居系として海上寮がありますが、高齢となっても一定の精神疾患がある場合老人ホームでは受け入れてもらえない場合が多く、それらの方には終の棲家となっています。
公共の福祉政策に大きく影響を受けると思いますが、現場から見て障害者福祉政策の問題点はどこにありますか。
政策は予算を伴うもので、限定された税収の中で福祉にどの程度配分されるかに大きく影響を受けます。財務省は厚生労働関係の予算を抑制しようと考えているみたいです。今回の報酬改定でも知的障害の分野は増額になりましたが、赤字になる事業分野が出てきています。報酬が物価上昇を反映しておらず事業者の努力に任されています。
また、圧力団体の影響を受けてなのか、政策の一貫性がないことも問題です。前に話したように、私共では国の方針に従って入居系の利用者を出来るだけ削減して、グループホームに移すことについて数値目標を作って対応していました。しかし、今回の報酬改定では、なぜか入居系が増額されて、推進してきたグループホームが削減されてしまっています。
高齢者のデイサービスは民間の株式会社に参入を認めたので過剰供給となり閉鎖する施設も出てきています。当法人でも2つを一つに統合する計画です。この地区で他の法人によってコロナ前に計画された老人ホームが最近、建物はできたが開業できないでいます。これは地域の高齢者数がピークアウトし入居予定者数が減っている、働く人がいない、施設の建設費の高騰が要因と言われています。今後、特別養護老人ホームが余剰となり、廃墟になる可能性があります。
首都圏から少し離れた地域として、職員の就労の問題はどうですか。
私共の法人では570名の方が現在働いていますが、毎年の職員の採用には苦労しています。15年くらいには前には少なくとも30名の新卒者を採用することが出来ましたが、昨年は20名が必要なところ10名程度の採用で、今年はもっと厳しくなっています。人手不足は65歳までの定年延長と70歳までの再雇用で対応していますが、体力的な面と人件費の面では問題を抱えています。この地域は東京に近いこともあり、高校を出た若い人が東京に出ていき、地元には公務員や金融機関等の就職者以外は殆ど戻ってきません。もちろん、福祉に関心のある若者が保育士の資格を取ったりして入ってくることもあります。
私共では完全週休2日を取り、平均給与も全産業の全国平均よりある程度高く働きやすい環境があるためか職員の定着率が良くて一般的な施設の倍となっています。

職員寮が用意されています。
コロナ禍で相当影響を受けたと思いますが、その経験から何か変化したことはありますか。
コロナのクラスターが発生すると通所系の施設は一定期間閉鎖となり、入居系の施設でもコロナ患者は他の病院に入院することになってしまうので報酬が減収となり経済的に苦労が続きました。利用者の家族や職員に負担をかけないためにも、クラスターをとにかく出さないようにとワクチンを始め様々な対策を行いました。そして、現在も対策を重視して色々やっていますが、その中でも一番効果があるのは部屋の換気を十分行うことであるということに気が付き、あらゆるシーンで徹底的に換気を行うようにしています。インフルエンザ等の空気感染系の感染も防げていると思っています。
施設を運営していて現在直面している対応課題はなにかありますか。
施設の運営面においては先にも話しましたが人手不足の問題とインフレに対応しない報酬制度等があります。利用者に対する対応としては、最近増えて来ている発達障害の利用者の方への対応があります。私共の発達支援センターでは発達障害に特化した相談と臨床心理士のカウンセリングに応じています。また放課後等デイサービスとして学校を終わった後に預かる施設、保育園として学童前の発達障害の子供に対応する施設、旭市の委託事業として親子で通ってくる施設があり順次その需要に合わせてプログラムを増やしていっています。これらの事業は子供という将来の社会を担う人の育成という大切な事業であると考えています。
敷地内にお御堂が設置されていますが。
敷地内には小原ケイ記念聖堂というお御堂があります。小原ケイさんは買い戻しに協力した4人の女性の一人で社会福祉法人ロザリオの元后会の初代の理事長を歴任した方です。現在は毎週日曜日に銚子教会の渡辺神父様にミサの司式をしていただいています。



お御堂の設計は師イエズス会のシスター北爪によるものです。
この事業に関わっていてよかったと思う瞬間はどのような時ですか。
売上とか利益というものに民間企業ほどはこだわらないで経営ができて、直接に利用者の方やそのご家族の方の喜びが伝わってくるところがこの仕事をやっていて良いところであると思います。障害者の方々と職員が笑いながら一緒に何かをしている光景を見ているだけで、私の方も癒される感じがします。特に知的障害の方は気持ちがそのまま伝わってくるので、私共が日常忘れてしまった純粋で無垢なものを持っていて、私はそれらの人といると心が休まり、自らを省みる気持ちになります。
インタビュー終了後に旭市の本部敷地内の就労系の施設「みんなの家」のパン工房と喫茶ひまわりを案内していただきましたので、写真を中心にレポートしていきます。

就労促進事業所「みんなの家」の竹内さんにパン工房を案内してもらいました。



工房の中には本格的な製パン設備が整っています。職員の方5名、利用者の方17名で、毎日朝5時半から食パンを約120欣、約40種類の菓子パンを焼いています。日によってはサンドイッチ、ロールケーキ、お菓子類を作ることもあります。1人の職人さんの指導の下、利用者の方が分業して各々得意分野の仕事を丁寧に行う結果、評判の良いパンが毎日焼きあがります。


工房で焼かれたパンは施設内の直売所「ぱんやさん」を始めとして、地元のスーパーや道の駅、企業や県立匝瑳高校等にも配達され販売されています。


喫茶ひまわりです。厨房では利用者の方が調理を行い、サービスも利用者の方が職員の方と一緒に対応しています。麺類やご飯もの等食事もできます。施設の方以外にも地元の方も食べに来ていました。

はーとふるメッセ・オブ・ザ・イヤーで審査委員特別賞を受賞したスティクチーズケーキです。
まろやかな甘さと濃厚なクリームとチーズの香りがして大変おいしかったです。




